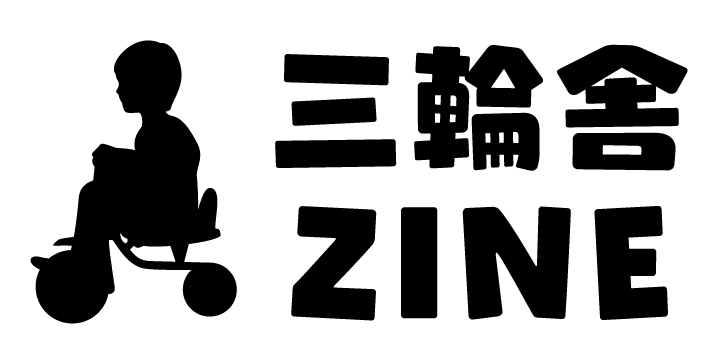わたしはゲラを待っている。予定から34日(!)経ったが、ゲラはまだ来ない。
ただ、製本の方向性については、すこし進展があったようだ。中岡さんは、この間に製本会社に行き、どんな用紙で、どんな造りの本にするか、現場の意見を聞き、「束見本」をつくってもらうことにしたようだ。
いたずらに色数が多くないほうが、想像力が働いていい
束見本というのは、実際に印刷するのと同じ用紙でつくる見本のこと。「束」というのは本の厚さのことで、中身はスケッチブックのように白紙だ。本のモノとしての佇まいを確認する重要な工程で、束見本にカバー案・帯案を巻き付けて、レイアウトを調整するデザイナーも多い。
中岡さんは直接製本会社を訪ねたようだが、ページ数が確定したところで、印刷会社に依頼して持ってきてもらうのが一般的なやり方だろう。もっとも、最近はソフトカバー(並製本、表紙に柔らかくて比較的薄い紙を使う)の本が増えていたり、使う用紙のパターンが決まっていたりすることも多く、この工程は端折られることも少なくない。
つまり、この絵本は、すこし特殊なつくられ方をしている。
「児童書版元ではない三輪舎が、どんな絵本をつくるのか」をテーマに、中岡さんは造本になみなみならぬ想いを傾けている。それが、ゲラが遅れる理由にならないことは言うまでもないのだが、あぁ、言ってしまった……。それはさておき、ぼくはその点は同じ本づくりに取り組む者として、とても共感し、敬意を持っている。
この絵本も、もともとは児童書の出版社でつくる想定だったので、絵は当然フルカラー、ページ数も40ページくらいが想定されていた。しかし、中岡さんは、企画を一緒にやることが決まった最初のほうの打ち合わせで、小林さんにこう言った。
「色数は減らしていいと思っているんです。いたずらに色数が多くないほうが、想像力が働いていいと思うんですよ」
異国の物語で、かつ歴史の話でもあるので、ふつうはむしろフルカラーを選びたくなるような気もするのだが、異国の物語で、かつ歴史の話であるだけに、僕はとてもおもしろい考えだなと思って聞いていた。実際に絵を描くことになる小林さんも、「おれもそれをやりたいんだけど、なかなかやらせてくれないんだよ」とおもしろがって、セピア調の、大きくは2色の原画ができあがった。ちなみに、このイエロー。小林さんの絵画教室では、デッサンの次に習う色の使い方だ。

さらに、中岡さんは、「絵は、ゆったり読めるほうがいいと思うんですよね」と、わざわざページ数を50ページ超に増やしている。この点も、少なくしようとするほうが多いのではないかと思われ、実は個人的にはすこし驚いていた。
そして、印刷がまたまた常識破りなのだが——、本題から離れすぎたので、話を戻そう。
「全ての道はローマに通ずと言うけど、あれはイスタンブルのことだと思うな」
さて、トルコとの出逢いだった。きっかけは、明確に小林さんの一言だ。
「あの国には道がある。あれは見ておいたほうがいい」
17年前の当時、ぼくは23歳。大学4年生だったろうか。青年末沢は、世界横断旅行の旅に出るか、ひとつの国に長く滞在するか悩んでいた。あの国というのがトルコだった。
ただ、ぼくと小林さんの出逢いは、トルコではなく、アフガニスタンがきっかけとなっている。
今20歳のひとはおそらくコロナ禍が、30歳のひとは東北の震災がそうなのだろうが、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロを20歳で迎えたことが、ぼくの人生の転換点となった。
既成の価値観が、ビルとともに音を立てて崩れていくような感じがして、これから社会が変わる予感を抱いていた。
時はITバブル全盛期。友達くらいの範囲でも、IT起業家がごろごろ生まれ、やたらにギラギラしていた。ぼくは完全なるIT音痴ではあったが、大学生のころ、有志がつくったインターネット放送局の代表を務め、動画の番組作りをしていた。
当時はインターネットがブロードバンドになった頃で、大容量の通信ができるようになったタイミング。その頃は、素人でも機材さえあれば、動画編集ができ、インターネット上で公開できることが時代の最先端で、ドキュメンタリー制作のサークル活動なども活発だった。今でこそ全てケータイひとつでできるが、YouTubeなどまだまだ夢の時代の話である。当時、戦場ジャーナリストに漠然とあこがれていた僕は、アフガニスタンにボランティアで行けることになったことをきっかけに、インターネットでアフガニスタンについて伝える番組作りを行った。
その過程で出逢ったのが、小林さんだった。出逢いは、強烈に印象に残っている。
まず、都内のテレビ局のカフェで待ち合わせることになったのだが、小林さんは下駄を履いていた。それに、絵本作家というイメージからは想像できない強面。義足支援のボランティアに同行することになっていたのだが、小林さんは、開口一番「義足は兵士を生み出すんだぞ」と言い、ぼくは一緒にいた先輩とともに度肝を抜かれた。実際、戦乱の長く続いたアフガニスタンでは、義足を得ることで戦地に復帰する兵士がいて、義足=いいこととは言えないんだよ、世の中のいいことも、悪いことも、裏側から見てみなさい、ということを小林さんは教えてくれようとしていたのだと思う。
その後も、会うたびに小林さんの常識を覆すような発想や発言に触れることになり、僕はいつしか人生の師匠と思うようになっていった。そして、小林さんがすすめる場所を訪れては、帰ってきて小林さんから話を聞き、また次の場所を教わって旅に出る、というサイクルを繰り返すようになっていく。
それで、出逢って3年後くらいにパキスタン、アフガニスタン、イラン、トルコと小さな横断旅行をした後、さあ、次は、いよいよ世界横断旅行の旅に出るか、それとも、ひとつの国にじっくり長く滞在するか、と悩んでいたのである。振り返るとモラトリアムも甚だしいが、当時はぼくに限らず、こうした無目的な旅がよく行われていたと思う。
正直なところ、本当は、ぼくはアフガニスタンに住みたかったのだが、当時も治安はかんばしくなく、トルコをすすめられた。ただ、トルコは世界を見るうえで、とても魅力的な国だった。
というのも、ひとつは、トルコ民族が世界中にちらばっていることだ。トルコ語は実は知られざる世界言語で、トルコ系の民族は、東は中国、西はヨーロッパまでいる。もちろん、アフガニスタンにもいて、このひとたちとトルコ語で会話ができたり、取材テーマとして追えたらおもしろそうだと思った(実際、ぼくはアゼルバイジャン人とはある程度会話ができる)。しかも、文法も日本語と近く、習いやすいのも、ヨーロッパの言語しか知らない当時の自分には開眼で、新鮮だった(一方、どんどんマニアックになっていくわけだが)。
もうひとつは、アナトリアの大地の歴史の重層性。アナトリアとは、トルコのアジア側地域のこと。これが小林さんの冒頭の発言「あの国には道がある。あれは見ておいたほうがいい」につながるわけだが、「トルコ」と聞くとイメージがわかなくても、そこには、メソポタミア文明があり、ビザンツ帝国があり、オスマン帝国があり……、と人類の文明の長い長い時の堆積がある。無数のひとが行き来した道があるのだ。
「全ての道はローマに通ずと言うけど、あれはイスタンブルのことだと思うな」と小林さんは言い、ビザンツ帝国時代のマイルストーンがあると教えてくれた。
実際、イスタンブルのまちを訪れると、観光地の一角にマイルストーンは目立たずあり、標識のような柱がすくっと立っている。その標識にはバラバラの方角を向いた矢印がついていて、矢印はバビロン、モスクワ、ロンドンなどへと向けられ、そこへの距離も書かれている。
そこに立つと、ふしぎとどこへでも行けそうな気がしてくるのだ。
2021.2.12 末沢 寧史