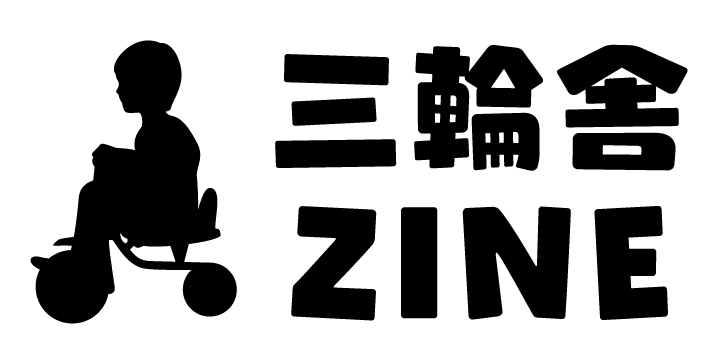2021年2月19日
わたしはゲラを待っている。予定から41日経っても、ゲラはまだ来ない。発売予定の3月上旬は、日に日に近づいている。しびれを切らして連絡すると、驚くなかれ、中岡さんも「実はゲラを待っている」と言うではないか!
それは本当なのか? だれを待っているのか?
その話はおいおいするとして、ぼくたちはトルコの話を続けよう。今回は、早めに本題に入る。
はじめてトルコにたどりついたころのぼくは、画家にあこがれていた。より正確には、小林さんにあこがれていた。
アフガニスタンを訪れて以来、ジャーナリストとして非日常の「ニュース」を伝えることよりも、ひとびとの日常の「日々」を伝えたいという気持ちが強くなっていき、その表現方法を模索するようになった。
アフガニスタン訪問は、圧倒的な異文化体験だった。
ぼくが初めて訪れた国はアメリカで、大学1年のときに参加した留学プログラムだったが、日本とのカルチャーギャップのなさにむしろ驚いていた。しゃべる言語は違うのだが、室内はエアコンがきき、コンクリートの建物で暮らし、合理的な発想をする議論好きのひとびとがそこにはいた。
一方のアフガニスタンはといえば、結婚はお見合いがいいと大学生が平然と言う前近代も甚だしい国である。道路は未舗装、住む家は日干しレンガ、首都カーブルはほこりと排気ガスにまみれていた。路上には、ひとびとの生活がむき出しになっていて、散髪する理容師がいれば、車やバイクを直すエンジニアがいる。オフィスワークの多い日本とは全然ちがい、むき出しの、迫力のある生活感が迫ってきた。

小林さんが描いた絵本『せかいいちうつくしいぼくの村』と『ぼくの村にサーカスがきた』の連作を見ていただければわかるが、アフガニスタンは日本と同じように春夏秋冬が巡り、それぞれの季節のうつくしさがある。アフガニスタンにハマったぼくは、ボランティアにかこつけて、四季制覇を密かな目標とし、2002〜03年に4回訪れた。
戦争はひとびとの生活のいたるところに暗い影を落としている。その一方で、愛車をデコるように愛自転車をデコり愛でる人がいたり、旅人をもてなす文化が強すぎてレストランなのにお金はいらないよと言う人がいたりした。いまだにその体験は記憶に新しく、アフガニスタンが恋しい。
そんな、ひとびととの日々はたまらなく新鮮で、現代的なぼくたちの生活とは異なる生のリアルを宿していた。その生きることのリアリティを表現してみたくなった。そして、「北緯36度線」をテーマに、それを世界中の国でやってきたのが、小林さんであり、それを可能としていたのが絵画という手法だった。旅をしながら暮らす生活にあこがれたのだ。
ただ、元来、美術は学校の成績が悪く、絵もへたである。当初は画家や絵本作家になりたいというよりは、小林さんのものの見方を学んだジャーナリストになろうと考えて、「ものの見方を教えてください!」とたのみこんだ。小林さんは、「それなら、絵がいちばんいい」と言って、賛成してくれた。かくして2003年ごろから本格的に絵画教室通いがはじまった。
5年ほど通っただろうか。
主にやっていたのは、静物や季節の植物などのデッサン。旅のスケッチをもとに絵を描いたりもした。ものの重みはどう表現するか、存在を白黒の2色でどう立ち上がらせていくか、いかに鑑賞者の視線を画面内に遊ばせることができるか、というようなデッサンの基礎を、手を動かしながら学んだ。とにかく自分で行けるところまで描いてみて、小林さんがまだ行けるところを示していき、また自分で行けるところまで描いていく——ということを繰り返した。
絵は感覚的に描くものとばかり思っていたが、その過程で、人の視覚の認知をふまえて、ある意味、科学的に構成される部分があると初めて知り、その奥深さにどんどんのめりこんでいった。絵画教室では、一枚の絵を描きあげるのに、半年くらいかける。その絵はいつも描き出しの入口と、完成の出口でまったく別物になっていた。小林さんは、「うまい絵は子どものころからやらないと描けない。でも、いい絵なら大人からはじめても描ける」と言っていたが、実際に手数をかけるとよい絵に仕上がっていく。
そこからが不思議なのだが、小林さんに絵画を教わると、自分が画家になれる気がしてくるのだ。子どものころから絵画教室に通う同世代も同じことを言っていて、それが教授法にあるのだとわかり、はっとさせられたことがあった。
そのひとの個性をいかすとか、のばすとか、そういうことではなくて、小林さんはつねに、その場にいる「ぼく」に対してというよりは、「ありえるぼく」という可能性に語りかけながら、絵を深めていくような教え方をしていた。すると、自分ひとりではたどりつけない場所に、導かれていくのだ。ぼくのなかに、いや、だれしものなかに眠っているのだが、はたらきかけ続けなければ死蔵していく感覚。そこに、目覚めよ、と、はたらきかけられていくのを感じていた。
そうすることで、少しずつ絵画が読みとけるようになっていったし、そこで教わったこと——たとえば、「仕事はこなしてはいけない」と小林さんが言うとき、100枚の瓦屋根が絵のなかにあれば、それを全部描き分けていくことを意味する——はあらゆる仕事と通底するところがあり、人生の糧となった。
そうして画家になりたい気持ちがむくむくと首をもたげていくわけだが、それなりの進化があったとはいえ、自分はどうやっても絵の才能がない。では、文章なのか、カメラなのか、映像なのか、なんなのか、自分に合った表現手段をみつけたい。
さんざん悩んでいたところで、出逢ったのが、「エブル」というトルコの伝統絵画だった。

エブルは、日本では「マーブリング」として知られている。水面に描いた模様を紙に写しとるトルコの伝統的な装飾画で、イスタンブルで発展し世界に広がった。イメージとしては、ラテアートのようなものを想像してもらうとわかりやすいかもしれない。
エブルと出逢ったのは、2006年。イスタンブルにあるボスフォラス大学で交換留学をはじめたころだ。大学院生だというのに研究はそっちのけで、大学にはほとんど通わず、日本の神社とよく似た聖者廟をめぐったり、少数民族の友達にインタビューをしたり、カフカスの難民キャンプのルポをブログに書いてみたりと、「留学」というより、「流学」の生活を過ごしていた。
ある博物館を何かの機会に訪れたとき、絵画の展覧会が目にとまった。そこに、それまでに見たことのない独特な手法でつくられた絵が並んでいたのだ。チューリップなどの伝統模様のようなものがあれば、砂漠の風景を描いたものもある。ひときわぼくの目を引いたのは、どことなく日本の海を思い起こさせる深い青色をした波の絵だった。
作ったのは、フスン・アリカンさんという女性作家。水の流線を写しとったようなその絵がどんなつくられ方をしているのか気になったぼくは、会場に置かれたパンフレットに作者のアトリエの電話番号が書かれているのを見つけた。翌日だったろうか、その電話番号に習いたてのたどたどしいトルコ語で電話をかけて、訪問させてもらう約束をとりつけた。

イスタンブルのアジア側までフェリーに乗り、トラムに乗って数駅進む。住宅街にあるアパルトマンの一室のアトリエで迎えてくれたフスン・アリカンさんは、まんまるくておしゃべりな人だった。エブルがどんなもので、どんな歴史があり、という話を、チャイを飲みながら楽しそうに教えてくれた。
エブルの歴史はとてもユニークで、中国で製紙法とともに生まれ、トルコ系民族の移動とともに伝わってきたという。しかも、日本にも墨流しという伝統模様があって、それが同じ技術を元にしているかもしれないとも教えてくれた。
まさにシルクロードの文化。話を聞くにつれ、わくわくがどんどん広がっていった。しかも日本人が誰も注目していない絵画手法である。見つけた。これは、運命だ!とぼくは思った。さらには、模様をつくるのに使うのは基本的に棒で、ペンや筆で描くわけではない。絵がへたな自分でもできるかもしれない、と思った。
ぼくがその場で「ぜひともエブルを習いたい」と前のめりに伝えると、フスン先生は「もう新しいコースは開かないから、最後の教え子になるかもしれないわね」と言って、あたたかく受け入れてくれた。「前にインド人の教え子もいたわよ」とも言っていた。後々知ったのだが、フスン先生は、エブルを伝統模様から解放し、新しい絵画手法として確立しようとしていた作家たちの中心にいる一人だった。
いざレッスンがはじまると、博物館で見たような現代風のエブルをつくってみたいと考えていたぼくに、フスン先生は「伝統的なエブルは道具づくりからはじめるのよ」と告げると、必要な材料のリストを渡し、バザール(市場)での買い物旅行へと放り出した。
意外な展開となったが、ぼくは一層わくわくした。筆、溶液、絵の具、用紙……。エブルに使われる材料の大半は世界最大の屋根つきバザール、グランドバザールや、香辛料屋が軒を連ねるエジプシャンバザールの近くにあった。
よく知られた観光地だが、観光では決して足を踏み入れることがないところにお店はあった。花屋に売れ残りのバラのくきをもらったり、モスクの広場にある屋台でじゅずのひもを買ったり。買い物自体が、異文化をめぐる旅だった。
画材屋に行けば、できあいの道具は売られていた。だけど、せっかく習うなら、伝統的なつくり方を知っていてほしい。買い物旅行には先生のそんな想いが込められていた。結果的に、ぼくはこの買い物旅行からはじまった1年間のエブルのレッスンを通じて、トルコという国、イスラームの文化について、いちばん多くのことを学ぶことになった。
ぼくはエブルをすっかり好きになり、日本で最初の作家になろうと決意した。
留学から帰国後、在籍していた大学院をあっさりと中退すると、最初は品川に住んでいた仲のいい先輩のタワマン(42階!)に居候しながら、北品川にある下宿の池田荘(仮名)2階の4畳1間をアトリエとして借りた。そのうち、(いつまでも出ようとしないので)タワマンを追い出されると、アトリエ暮らしをはじめるようになる。
当時はアルバイト生活で、年収は150万円あっただろうか……。裸電球ひとつしかない家賃3万円の小さな和室で、電気代はメーターの申告制。なぜか、住所は、池田荘2階左という謎の表記で、インターネット開通の際には、「そんな住所みあたりません!」とオペレーターに訝しまれたものである。
ある友達は、部屋を訪れ、あまりの貧しい佇まいに涙を流した。それほど詫びしき物件であり、生活だった。当の本人はただ夢を追いかけていたので、それはそれで「ひとりトキワ荘」妄想を広げながら、「10年かければなんとかなるんじゃない?」といたって高度経済成長期的な能天気さでいた。
しかし、時は平成の就職氷河期、失われた20年。わずか1年たらずで心の骨が砕け散り、挫折することになるのであった。