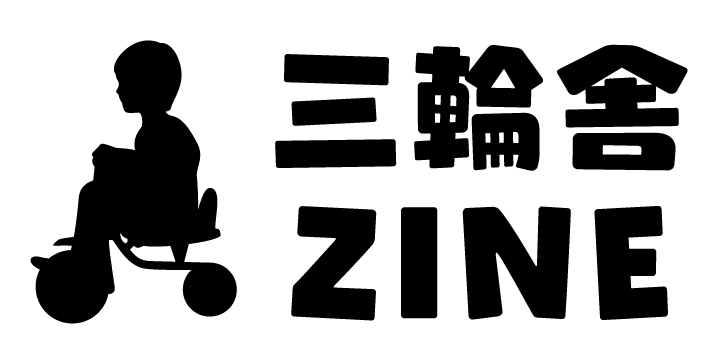2021.3.26
今日は、「求めるものは、目指した先になくてもいい」というテーマでこの連載をお届けしたいと思う。
「次のゲラはいつだ?」と、3月19日に書いた連載の最後でぼくは問うた。これはもちろん、編集者の中岡さんへの問いかけだったのだが、この原稿を書いている26日時点で、刊行までのスケジュールや次の段取りの具体的な連絡は来ていない。だが、ことさら、それを咎めようとして書いているわけではない。
思わぬところから、進捗が伝わってきたからだ。
前回の記事で、三輪舎の刊行物のスケジュールが遅れに遅れる「カタツムリ理論」を解明したところ、関係者のあいだで局地的な反響を呼んだ。
「実は、このふたりこそが「カタツムリ」の化身であり、お互いに締め切りをのばしあっていたのだ!!」
— 川内有緒 新刊「バウルを探して 完全版」 (@ArioKawauchi) March 23, 2021
ウケる。カタツムリ2人を制して無事に本を出せた自分を褒めたくなった。末沢さん頑張れ〜。 https://t.co/9AeU6FKMse
三輪舎で『バウルを探して〈完全版〉』(2019年6月)を出版したノンフィクション作家の川内有緒さん。『海峡のまちのハリル』はこの本と同時刊行と言われていた。
松沢さんの連載が面白い。どう面白いって自分もまあ似た体験をしたものだから。クリスマス商戦、うんどこかでぼくも聞いたなあ(笑)。という話はきっと明日のトークには出てこないと思う(そんな話に割り振る尺はない笑)。ともあれ、この本が無事この世に誕生しますように、心から祈ります。 https://t.co/yfHPmj7Eda
— してきなしごと ウチダゴウ (@uchidago) March 22, 2021
三輪舎の近刊『鬼は逃げる』(2020年12月)の著者、詩人のウチダゴウさんも似た経験をしたと語る。ただし、より遅くスタートしたウチダさんの本が先に出ている。
石版多色刷りの装画を多数添えた夏目漱石『漾虚集』では、画家中村不折のこだわりもあって、色校正が遅れに遅れた。
— 桂川 潤 Katsuragawa, Jun (@jun_soutei) March 25, 2021
漱石は「漾虛集はまだ出來ず本屋がむやみに校正を後らす故に候」とぼやいている。『#海峡のまちのハリル』の著者・末澤寧史さんも、同じ思いだろう。 https://t.co/ji2DVgZ3m5
装丁家の桂川潤さん。小林さんの作品『ぼくはチョパンドス』(光村教育図書)は桂川さんがデザインしている。無職時代に装丁の仕事場を見せていただいたことがある。
偶然の装丁家、(締切)前夜の装丁家などいろいろな異名で呼ばれてきたぼくですが、このたび「カタツムリの化身」というあらたな名まえをいただきました…! https://t.co/HkqtI73yYD
— 矢萩多聞 (@tamonya) March 23, 2021
「カタツムリの化身」となった矢萩多聞さん
3月23日。「本当の締め切り」を待つ矢萩多聞さんから、Twitter上で「中岡さんとはスーパーかたつむりブラザーズです。あとは造本仕様が決まってくれれば、外回りも手がつけれるのですが…」というコメントがあり、それへの応答として、ブラザーズ弟(?)の中岡さんから「今日笠井さんから重要な情報がもたらされました。またお知らせします」という匂わせ投稿があった。
ちなみに、「笠井さん」とは、『日日是製本』というZINEを手がける製本職人の笠井瑠美子さんのことで、今回の絵本の束見本をつくってくれている(三輪舎の『本を贈る』の共著者で、本のヌード展でも「本の解体SHOW!」に協力してもらっている)。
その後、分版について紹介した藤原印刷の藤原章次さんに前回の掲載記事を紹介したところ(やはり中岡さんから連絡を待っていたようなのだが)、翌24日に「中岡さんから電話来ました笑」というメッセージがぼくのもとに届いた。「日曜か月曜かに」納得のいきそうな束見本が来る、と中岡さんは言っていたそう。日曜は3月28日、月曜は29日のことだ。
印刷会社から次のスケジュールを知る、あっと驚きの展開ではあるのだが、これらを総合的にひもとくと、こういうことだ。
みなさんがこの原稿を読む今週、造本が決まり、したがって表紙デザインも決まる。
ついに、である。ひゃあ。
ちなみに、多聞さんは、出版業界では表紙のラフ案をたくさん出すことでも知られている。以前、足を運んだ装丁展では、実際に装丁された本だけでなく、読者としては知るよしもないボツ案もたくさん展示されていてとても面白かった。最後の一案にたどり着くまでに、ものすごく手が入れられていることがわかるのだ。オアシスのうつくしさは、人が目を行き届かせ手を入れることで保たれるという。多聞さんの装丁も、その意味で、オアシスのようだった。今回は、小林さんの絵をもとに、表紙案はつくられることになる。どのように手が入れられていくのか、とても楽しみだ。今日、その表紙案をここでお見せできないのは残念ではあるが、採用されなかった案もいつかみなさんに見ていただける機会があってもまた楽しいかもしれない。
話をまとめると、ぼくが求めていたスケジュール連絡は印刷会社からやってきた。目指した先にいつも求めるものがあるわけではない。それでいいのだと思う。
表現者になりたかった
トルコでエブルに出逢い、エブル作家になろうと一歩を踏み出したのは26〜27歳のときだった。だが、そもそもは小林さんのものを見る目線や、表現の手法を学び、小林さんのような絵が描ける画家になりたい、というのが根本的なモチベーションだった。なので、帰国後も4畳半の自宅でのエブル修業のかたわら絵画教室には毎週通いつづけていた。
半年くらい過ぎたころだったろうか。やはり画家になりたいという思いは日増しに募るばかり。ぼくはとうとう腹を固め、小林さんに宣言した。
ある土曜の夕方。絵画教室が終わり、小学生の子どもたちや、少し年齢が上の高校生などがいなくなったあとだった。小林さんは画材を片付けていた。緊張しながら、ぼくは「ちょっと話があるんですが」と声をかけ、「やはり画家を目指したい」とそのときの気持ちを率直に伝えた。作業の手を止めた小林さんは、ぼくを真っ直ぐ見つめてこう言った。
「無責任なことしか言えないけど、俺は賛成だよ」
満面の笑みだった。
小林さんは、下手な絵でも原稿でも、講評してもらいたくて持っていくと、いつも否定するということがない人だった。表現するという行為を全肯定しながら、アドバイスをくれた。当時のぼくは、小林さんから「賛成」の言葉を聞きたくて、そう言ったのかもしれない。小林さんにさえ認められれば、それでいい。誰に何を言われようが、10年頑張ってみよう。そんな意気込みだった。それまでの人生は、頑張れば、大体の目標は達成できたし、人生なんとかなると思い込んでいた。
しかし、これが、人生のレールを大きく踏み外した瞬間だったのだ。2000年代後半、就職氷河期の真っ只中。手に職もなければ、起業するわけでもなく、そもそも就職を投げ捨てるという捨身の挙に出ていたことに、当時の自分はあまり気づいていない。
「じゃあ、練習にまず絵を100枚描いてみな」と、小林さんに言われ、まちに繰り出してスケッチをしてみる。だが、思うような画題や構図がみつからない。捨身の挙を心配した小林さんの奥さんがぼくに引導を渡そうと、「画家は才能よ」とやんわり耳元でささやくことも一度ならずあった。いろんな人と話すたびに、早くふつうに就職しなさいと注意された。
だが、もはや盲目の修行僧であるぼくの耳にそれらの言葉は入ってこない。だが、やはり絵はいつまで経っても描けるようにならなかった。
「絵本を描いてみるか?」と小林さんに言われ、アフガニスタンの子どもたちに見せようと持っていったことがある自作の紙芝居を見せてみる。だが、プロの目線で見てもらうと、「展開が足りないな」の一言で終わる。
日に日に行き詰まっていくなかで、小林さんには、「おれが絵を描くから、文章を書いてみたらどうだ?」とまで言っていただいた。だが、願ってもないチャンスのはずが文章も書けない。新聞社の学生記者などもしていたから、文章にはそこそこ自信があった。絵本は、いつか書いてみたいとも思っていた。それが、まさに目の前にチャンスがあるというのに、絵本にできるテーマがまったくみつからないのだ。
表現者になる! 会社なんかで働くものか! などと、気負えば気負うほど空回りし、現実とのギャップがどんどん自信をむしばんでいった。まわりの友達は続々と社会に出て、それぞれのキャリアのなかで舞台を得て活躍をはじめていく。同年代が卒業すると、後輩たちも、ぼくを追いこして就職を決めていく。
自分はといえば、たとえ夢を追いかけていようが、現実には単なる「無職」だった。しだいに焦り、周囲の一足早く就職してきらきらと活躍しはじめる人たちを恨み、「あいつより、おれのほうができるはずなのに!」などと、のろいはじめていく始末だ。
そんな、ある日、久しぶりに電話で話した知人に「画家修業? まだ、そんなことやってるの?」と言われたことがきっかけだったろうか。急に絵が描けなくなった。その人は心配して言ってくれただけなのだろう。だが、自信を失いつつあった心に、その言葉はよく切れる包丁のようにすっと入ってきた。
そのころ、ぼくは新聞社でコピー取りのアルバイトをしていた。アルバイトの合間に絵の練習をしようと、いつもスケッチブックを持ち歩いていた。その日も同じように、アルバイトの休み時間にスッチブックを開き、デッサンの練習をしようとした。だが、鉛筆を握る手が震えて動かなかった。
タバコ部屋に移り、灯りもつけ忘れて、タバコを吸う。「おれ、何がしたかったんだろう」。なんだか泣けてきた。
タバコ部屋に後から入ってきた、デスク(新聞社の次長。ニュース記事の編集担当者)のおじさんが灯りをつけて、「きみ、なんか思い悩むことでもあるのか?」とにこやかに聞く。ぼくは「いえ、別に」と動揺に気づかれないようにしながら立ち上がると、足早に部屋を出た。
「まず、生活を立て直さなければ」。この日、ぷつりと糸が切れ、ぼくは小林さんには一言も告げず、絵画教室を去った。
トルコという「夢」
こうして、人生をかけて追いかけようとした“夢”は叶わなかった。だが、目指した先に求めるものなどないのかもしれない、とぼくはいま思っている。それでも、小さな夢は持つことができる。それもたくさんの夢だ。
紆余曲折を経て、編集者として一人前になり、それなりにヒット企画にも恵まれるようになっていた2015年のある日。とあるポスターを美術館で目撃したことが、トルコの夢を復活させた。
その美術館とは、東京・渋谷にあるワタリウム美術館。この美術館は、キース・ヘリング、ヨーゼフ・ボイスをはじめ世界の最先端のコンテンポラリーアートをいちはやく日本に伝えてきた。
変人=独創こそが世の中を創造的に変えていく、ということをテーマとしたアーティスト・椿昇さんのユニークな教育書『飛び立つスキマの設計学』(産学社)をつくった際、ワタリウム美術館CEOでキュレーターの和多利浩一さんを取材させてもらい、刊行後に対談イベントを地下にある書店で企画していただいた。
そのとき、現代アートの美術館にもかかわらず、「山田寅次郎研究会」と書かれた大きな赤いポスターが柱に掲示されているのを偶然目にしたのだ。

山田寅次郎(1866〜1957年)といえば、トルコ関係者は誰もが知る、歴史上の人物である。エルトゥールル号事件の義捐金をトルコに届け、その後、トルコに滞在しながら民間外交官として活躍し、日土友好の礎を築いた立役者として知られている。
だが、なぜ、現代アートの美術館で、山田寅次郎を研究するのか。
和多利さんに聞いてみると、奥さんでディレクターの月子さんが、山田寅次郎の実孫だという。ワタリウムではそれまでも南方熊楠、岡倉天心、伊藤忠太など、明治の知識人や文化人の再評価を行ってきている。その流れもあり、山田寅次郎という人物の知られざる面白さに着目したという。
月子さんに話を聞いてみると、「祖父はすごく変わった人だった。よく知られていること以外にも、出版ビジネスに取り組み、オスマン帝国皇帝に日本文化を紹介し、日本初のシガレットペーパー製造会社をつくり、茶道家元として流儀を革新し……と、多様な顔を持つ人だった」と聞かせてくれた。
そして、研究活動にかける思いを、「祖父の偉人像を解体し、等身大の姿で伝えたい」と熱心に語っていた。「それが、今の若い人にとっても一つのロールモデルになりうるのではないか」と。
ぼくは現代アートはまったくの門外漢だが、そんな話を聞きながら、研究会の書籍化は自分がやらねばと考えていた。おそらくこの機会を逃すと、トルコを仕事とするきっかけはもうないだろうと感じていた。 「企画が通らなかったらボランティアでもいいから、出版をやらせてください」と月子さんに頼み込み、会社で企画を通した。
その本が、『明治の男子は、星の数ほど夢をみた。―オスマン帝国のアートディレクター山田寅次郎』(産学社)だ。

この「明治の男子」という表現は、寅次郎がよく使った「男子たる者は」という言葉にちなんだもの。明治男子の大志に学びつつ、その夢の大きさを語るのもよいけれど、どれだけ多くの夢を持てるかに、この閉塞する時代の突破口を見出したい——。そんな思いをこめて世に送り出した。
山田寅次郎という人物は、若いころは政治家を目指して挫折したり、流行りの機械潜水に挑戦したり、海外に行く口実が欲しいところもあって義捐金活動をしていたりと、極めて人間的な動機を持ちながら、周辺状況にあわせて己の姿を変転させ、夢を一つひとつと軽やかに叶えていく。
そんな生き方に、画家をあきらめ、ライターとなり、編集者となり、と流れ流れ生きてきた自分のあり方もどこか重ね合わせていた。かつての自分に夢は星の数ほどもっていいんだよ、と語りかけたかったのかもしれない。
月子さんは、山田寅次郎研究会を発展させ、今はオスマン帝国時代の文化を紹介する「山田寅次郎 オスマン倶楽部」というプログラムを主宰している。久しぶりに連絡をとってみたら、トルコのテレビ番組で祖父の足跡を紹介したことをきっかけに、世界遺産で有名なトルコ中央部のカッパドキアにあるカッパドキア大学で「山田寅次郎教室」をつくることを依頼されたという。拠点は、大学が所有する14世紀につくられた「マドラサ」という昔のイスラームの学校。そこから、日土の文化交流プロジェクトを立ち上げる準備を進めているそうだ。日土交流のDNAは、時を超えて受け継がれている。トルコやオスマン帝国の文化に関心のある方には、ぜひこの動向に注目していただきたい。
さて、こうして、新たな人生のロールモデルも見つけ、ぼくは表現者として生きたいというかたくななこだわりはもたなくなった。書籍編集の仕事は刺激的で、十分魅力的だったし、それなりに満足ゆく成果も出せていた。だいたい、向かないことを無理して続ける必要などない。
では、なぜ、10年もかけて1本の絵本原稿を推敲し続けてきたのか。この連載の最後となる次回に書こう。