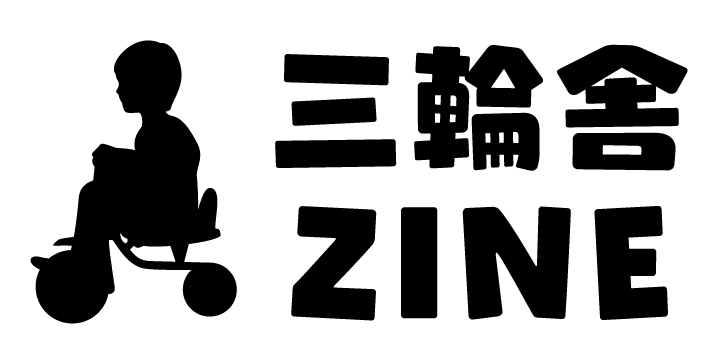2021.4.3
「社会が『わかりやすさ』を求めるようになって、わかったつもりになることも多い。でも、わからないってことが本当は大事なんだ」
小林さんからその言葉を聞いたのは、いつだったろうか。
わからないことに飛び込むことで、世界はひらかれていく
今回は、どうしても書くのに時間がかかってしまい、日にちをまたいでしまった。実はちょっとだけ忙しい。春だ。SNS上に桜の花びらのように舞っていた年度始めの報告というものをしてみたい。ぼくは今、おもしろカオスな仲間たちと、出版社を立ち上げようとしている。会社はすでに法人登記を終え、いよいよ今月初めての本を出す。
本当は、『海峡のまちのハリル』が出るのが先だろうと思っていたが、どっこい、自分の出版社で出す本のほうが先になった。とはいっても、『海峡のまちのハリル』の制作も造本がいよいよ決まったようで、佳境に向かいつつあるようだ。まもなく、表紙案が来る。まだゲラは来ていない。だが、あとがきページのやりとりがはじまった。その原稿をいつ入稿したかは、覚えていない。
出版社を立ち上げた経緯は、いつか別の機会にご紹介することがあるかもしれない。この連載でお伝えしたい、というか、いまおおいに反省しているのが、出版社を立ち上げたにもかかわらず、書店営業というものが「わからない」ということだ。
いや、実は、小さな出版社で7年勤めていたから、営業担当に付いて書店を回ることもあれば、書店員さんとのやりとりで担当した本を仕入れてもらうことももちろんあった。飛び込みで営業をしたこともある。少しはわかっているつもりだった。だが、最初の本の営業を進めるにあたり、メンバーに出版営業の経験者がいないことから、別の出版社の敏腕営業の方にアドバイスを乞うと、自分は出版営業の「え」の字もわかっていないことが判明した。
まず、書店にFaxなどで送る注文チラシ。「営業が書いてよ」とぶーぶー言いながらも、小さい会社にいたから、自分の担当書籍の原稿は自分でだいたい書いていた。
ところが、その敏腕営業の方に「この本のジャンルはそもそも何ですか?」と聞かれた際に、的を射た返答ができなかった。会社にいたころも、営業によく聞かれた質問である。このときのジャンルというのは、「書店のどの棚に置くのか」という意味なのだが、その質問の意図が正確にはよくわかっていなかった。書店の棚構成のカテゴリーをみて大きな展開を考えよ、ということだった。
また、「類書はなんですか?」もよく聞かれる質問。これも、「同ジャンルで売れている新刊」を展開の材料にせよということだとつい先日初めて知った。
お恥ずかしや。
そんなことも知らないから、いざ初営業と、某大手書店に電話をしてアポとりをしようとしてみても、書店員の方に「忙しいから来ないでほしい」と冷たくあしらわれる始末だ。しかも、「1冊注文つけときますから」という、ぐうの音も出ない対応。1冊では、棚にひっそり置かれるだけで、その本が平台という陣取り合戦激しき主戦場で日の目を浴びることはほぼない。
まるで、土俵から押し出され、塩をまかれるような門前払い。塩のなかの塩対応とでも言うのであろう。だが、「せちがらい世の中だなぁ」などと嘆いている場合ではない。どうしたらよいのかわからなくても、そこであきらめたり、投げ出したりしてはいけない。読者がいると、信じるならば。
わからないことに飛び込むことで、きっと、初めて世界はひらかれていく。
希望
レールを脱線したあとの人生というのは、わからないことの連続だ。
27歳からの遅れた就職活動は思いのほか大変だった。情報交換し、励まし合うような同期はおらず、どうやって就職活動をすればいいのか、わからなかった。
そこで、とりあえず、ハローワークに行った。職員に「画家になりたくてアルバイト生活をしていたんですが、あきらめました。年齢要件は満たすので新聞社の採用試験を受けてみたいんですけど……」と相談をした。職員は、ほほう、来たな、ようやく現実を思い知ったフリーターめ、といった眼差しをぼくに向けた。そして、お前、まだ現実がわかっていないな、という表情で、「これなら紹介できますけど」と言って、校閲のアルバイトの求人票をすっと差し出した(校閲自体は専門性の高い大事な仕事であることは付言する)。
新卒としては確かに動き出しがあまりに遅い。でも、スタートが遅いだけで、チャンスがないのだろうか。納得がいかず、記者の友人のアドバイスを得ながら新聞社や通信社の入社試験を受けてみた。なんとか最終面接までたどりつくものもあった。だが、一度は就職をあきらめ、別の道を選ぼうとした人間の気迫のなさか、最後の最後でうまくいかなかった。
結局、学生のころに一度はあこがれもした報道の世界もあきらめざるを得なくなった。
「人生終わったと思うだろ? だけど、人生はそんなに簡単に終わらないんだな」
失敗してどん底だったとき、そう言って励ましてくれた人がいた。
ジャーナリストで、調査報道の第一人者として知られる高田昌幸さんだ。大学で教鞭をとりつつ、ぼくも関わる「フロントラインプレス」という調査報道集団を率いる高田さんは、当時、ぼくがアルバイトをしていた新聞社のデスクをしていた。友だちが大学で講演会を企画し、そこに参加した縁があり、遅めの就職活動を行うにあたり作文や面接について教えてもらっていた。ちなみに、見てもらった原稿が、ものすごい達筆で真っ赤に朱入れされて戻ってきたことを覚えている。
画家の夢は叶わず、就職活動も失敗に終わった。だが、人生は、確かに終わらなかった。
2009〜2010年のことだ。新聞社に就職できなかったぼくは、友だちの紹介でフリーペーパーを制作するベンチャー企業に就職し、ライターになった。だが、会社で働くということがどうにも性にあわず、1年もしないうちに辞めようとしていた。
そんなときに高田さんに声をかけていただいたのが、『希望』(旬報社)という書籍の出版企画だった。

その企画は、「あなたが希望を感じる人を取材してください」というテーマで、約20人の記者やライターが集まり、ロングインタビューから時代の相を描く、というものだった。インタビューの名手として知られたスタッズ・ターケルの『希望』が企画の下敷きとなっていた。
くすぶっていたぼくは、企画への参加を呼びかけるメールに即座に飛びついた。なにより自分こそが、希望を探していたのだ。取材対象の候補出しが行われたとき、ぼくが取材し、その存在を世に伝えたいと思ったのは、やはり小林さんだった。絵画教室を去ってから、2年が経過していた。
曲がりなりにもライターとして活動できるようになり、再会のきっかけを探していた。手紙を書くと、小林さんは快諾の返事をくれた。
当時の原稿を改めて読むと、自分は記事の主見出しを「自信はないよ。ただ、描きたいものがあったからね」という小林さんの発言からとっていた。
おそらく、その部分が一番、その時の関心に響いたのだろう。一部引用してみる。
「当時は(※会社を経営していて)忙しくてね。徹夜に徹夜を重ねることもあったな。それはそれで楽しかったんだけど、会社はコマーシャリズムに乗っていく部分があるじゃない。どこかでやっぱり絵を描きたいなと思いだしたのかな。そんな生活を3年ぐらい続けてから、『オレは会社を辞めて絵描きになる』と自分と周囲に宣言しちゃうわけだよ。宣言したからと言って、なれるわけではないけどさ。そうするって言った以上、そうするわけだよ。いわゆるアカデミーの教育を受けたわけではないから、自信はないよ。ただ、描きたいものがあったからね」
小林さんの話は相変わらず面白かった。こういう話を聞いてきた影響で、ぼくは画家にあこがれたのだ。だが、この取材自体がぼくのその後を変えたわけではない。
東日本大震災からまもない2011年7月に本が出版されたあとのこと。
できあがった本を小林さんに届けに行った。ちょうどそのとき、当時は老舗児童書版元に勤め、小林さんに企画の相談に行きたいと言っていた、まきこさんも一緒に自宅にお邪魔することになった。
絵画教室に使われる大部屋のテーブルを3人で囲み、取材のお礼を言って近況などの話をした。しばらくすると、まきこさんが、小林さんに企画の相談をはじめた。まきこさんは、「エネルギー問題の本がつくれないか」と提案をした。だが、小林さんは、あまり関心がない様子で、話はなんとなく流れていった。
一通り話が終わると、では、どこかで飲もうとなった。向かった先は、近所にある行きつけのエスニックレストラン。飲み会からは、小林さんの奥さんも加わった。
20席ほどの小さなお店だ。ビールやワインを飲み、ピリ辛な料理を食べながら、まきこさんが聞き手になって、小林さんが最近出版した絵本のことや旅の話などを語る。奥さんもその話に加わり、にぎやかな会話をぼくは楽しく聞いていた。
ぼくの仕事の話に会話が及んだときだったろうか。ぼくは、職業ライターの道を歩み出そうとしていた。初めての本を出し、自信を持ってその道に進もうと考えはじめていた。そんな話をしていたのだと思う。
小林さんが、急に話を切り出した。
「絵本をつくらないか。おれが絵を描くから、末沢くんが文章を書く。鈴木さんが編集すればいい」
ぼくは信じられない気持ちで、その言葉を聞いて呆気に取られていた。それは、2年前、もがいていたぼくに小林さんがかけてくれたのと同じ言葉だった。だが、それはあくまで状況を見かねての小林さんの優しさに過ぎず、夢のようなこととあきらめていた。
目の前にいる小林さんは、真剣な目をしていた。あのときの言葉は、本気だったんだと、ぼくはその時知った。表現をやめるな、ということだ。
その瞬間、胸にあついものが込み上げてきた。こらえようとするが、むりだ。ぼくは気づかれまいとして、トイレに駆け込む。飲み過ぎたのだろうか。涙が後から後から流れてくる。
小林さんの気持ちがありがたかった。
帰り道。駅へ向かう道を、小林さんは奥さんと手をつなぎながら仲良く歩いていた。その後ろをついて、まきこさんと歩く。駅につくと、別れ際にぼくは、小林さんに言った。
「何も言わずに飛び出して、すみません。あわす顔がなくて」
すると、小林さんは、ちょっと困ったような顔をして、「心配したぞ」と言った。「君が道を踏み外したことに責任の一端を感じている」とも。困ったときこそ、相談しろよ。そう言いたげでもあった。
10年前のこの日、ぼくは、小林さんから、何かを託されたと思っている。